●泌尿器科、皮膚科のパイオニア
明治17年(一八八四)、京都府生まれ。東京大学医学科を卒業後、大正7年(一九一八)から2年間、米国の大学に留学し、尿管の生理について優れた研究を行った。帰国後は、先進的な治療を取り入れ、大阪大学泌尿器科の近代化に努めた。人情味のある医師として看護師にも慕われたという。
博士は大阪大学、京都大学、京都府立大学と交流、親睦をはかるため、近畿皮膚科泌尿器科集談会を創立。肩のこらない気楽な会として、今なお引き継がれている。
ハンセン病の研究にも取り組み、阪大にこの病気を治療するための「特殊皮膚病研究所」を設立した。昭和12年(一九三七)、阪大付属病院長を経て、大阪国立病院長(現・大阪医療センター)に迎えられた。博士の業績をたたえ、中庭に像が残されている。昭和32年(一九五七)没。
佐谷有吉博士像
さたにゆうきちはかせぞう
次の言語でも読めます: English
投稿日:
所在地
大阪市中央区法円坂2-1 大阪医療センター内
交通機関
地下鉄谷町線・中央線「谷町四丁目駅」
施設情報
問合せ先:06-6942-1331
同じエリアにこんなスポットがあります!
-

サクラアートミュージアム
●大阪のまちにアートを発信 「サクラアートミュージアム」は企業美術館として、平成3年(一九九一)に本社ビル内に開設され、会社の歴史や描画材に関する資料が豊富に集められている。クレパス画約300点、油絵 …
-
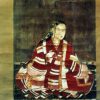
玉日姫像
●親鸞(しんらん)聖人の妻の肖像画 昭和50年(一九七五)、大阪府の有形文化財に指定される。桃山時代に描かれた肖像で、浄土真宗開祖の親鸞聖人が善信(ぜんしん)と名乗っていた頃の妻、玉日姫を描いている …
-

大阪英語学校跡
●大阪初の外国語学校 明治維新後、大阪では舎密(せいみ)局に始まった洋学校と理学校が合併し、大阪開成所が開校した。洋学教育の最先端校である。開成所は第四(のちに第三)大学区第一番中学、第三大学区開明学 …
-

大阪活版所跡
●近代印刷の幕明け 明治3年(一八七〇)、大阪商工会議所の初代会頭・五代友厚(ごだいともあつ)の要請を受けた本木昌造(もときしょうぞう)が創設した活版所の跡である。 木版印刷が主流だった頃は、印刷に莫 …
-

大阪城ホール
●城郭の隣に控える大ホール 「大阪築城400年まつり」のメインイベント会場として、昭和58年(一九八三)に建設された、多目的アリーナ。年末の風物詩「一万人の第九コンサート」など、さまざまなイベントが開 …












