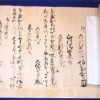大槻能楽堂
おおつきのうがくどう
次の言語でも読めます: English, 한국어, 简体中文, 繁體中文
投稿日:2011/11/25 更新日:
●能好きの太閤秀吉
とにかく能楽に熱中していた豊臣秀吉(とよとみひでよし)。自分を主人公にした「明智討」という能をつくらせている。会う人ごとに「宮廷でお見せする」と言って家臣にたしなめられたという逸話もあるほど、朝から日暮れまで大坂城で能を演じていた。鼓方の大倉流の家元には「シテ(主役)・太閤」と記された演目が残っている。大阪城に近い上町台地で能が演じられることは歴史的にも意味深いことで、舞台の橋掛かりの壁には実物大の大阪城の石垣が描かれている。
●能楽堂の舞台裏
大槻能楽堂では観劇後、バックステージツアーを催している。能舞台の構成や仕組みの説明から始まり、音響をよくするため舞台下に規則正しく配置された大きな甕(かめ)も見ることができる。めったに足を踏み入れることができない舞台裏や楽屋の一種独特の厳粛なムードが体感できる。
●子どもと外国人とデジタル
世界遺産になった能をもっと広く知ってもらうため、さまざまな取り組みを進めている。「こどもとたのしむ能狂言」では解説付きで能を鑑賞、狂言や謡にチャレンジできる。鼓を鳴らしたり、装束を身につけたりできる、ワークショップもある。また、世界中の人々が鑑賞できるように、能のデジタル・アーカイブス化を進めている。
追加情報
●もっと深く知ろう!
【足拍子の音が響くのは?】
舞台の下には規則正しく大きな甕が埋め込まれている。これは舞台下の空間を広げ、舞台の足音の響きをよくするという音響効果のためのものである。
●高さ1m、直径1mの甕(かめ)
ホームページ
所在地
大阪市中央区上町A番7号
交通機関
●地下鉄谷町線/中央線 谷町四丁目駅
谷町線/長堀鶴見緑地線 谷町六丁目駅
施設情報
●問合せ先:06(6761)8055
同じエリアにこんなスポットがあります!
-

●若き日の聖徳太子による創建 「鵲森宮」は、通称、森之宮神社とも呼ばれ、聖徳太子(しょうとくたいし)が建立した。 その創建は、四天王寺や法隆寺よりも古いとされている。崇峻(すしゅん)天皇2年(五八九) …
-

●やはり秀吉は大阪城が似合う 豊臣秀吉(とよとみひでよし)、秀頼(ひでより)、秀長(ひでなが)を祀る神社。京都の豊國神社の別社として、明治12年(1879)に中之島に創建されたのが始まりである。昭和 …
-

●近代上方漫才の原型をつくった作家 「大阪漫才の父」。歌碑文は、「渡りきて浮世の 橋を眺むればさても危うく過ぎしものかな」。玉造稲荷神社は秋田實の子どもの頃の遊び場。明治38年(一九〇五)生まれ、昭和 …
-
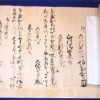
慶長20年(=元和元年、1615)に起こった大阪夏の陣、とりわけ大阪城から南に連なる上町台地一帯で繰り広げられた5月7日の最後の決戦は、豊臣家の滅亡をねらう徳川幕府軍15万5千人と豊臣方5万5千人が …
-

●城郭の隣に控える大ホール 「大阪築城400年まつり」のメインイベント会場として、昭和58年(一九八三)に建設された、多目的アリーナ。年末の風物詩「一万人の第九コンサート」など、さまざまなイベントが開 …